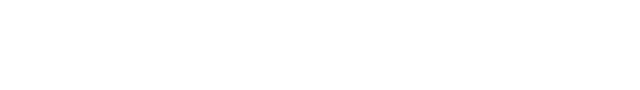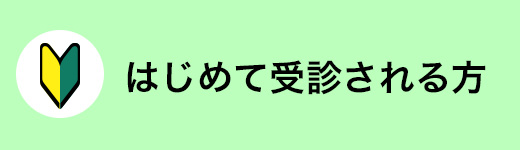夏の冷えすぎに要注意!胃腸が冷えて不調になる理由とは?
「暑いから冷たい飲み物をたくさん飲む」「エアコンを効かせて快適に過ごす」──夏の日常では当たり前のことですが、こうした生活のなかで知らず知らずのうちに「胃腸の冷え」が起きているのをご存じでしょうか?
今回は、夏でも注意が必要な「胃腸の冷え」について、その原因と対策をわかりやすく解説します。
胃腸は「冷え」に弱い臓器
暑い夏に「冷え」と言われてもピンと来ないかもしれません。しかし、冷たいものをたくさん摂ったり、冷房の効いた室内に長時間いたりすると、体の表面は暑くても内臓は冷えてしまうことがあります。
特に胃腸は、消化や吸収を行うために一定の温度が必要です。冷えすぎるとその働きが鈍くなり、以下のような症状が現れることがあります。
- 胃のもたれ・膨満感
- 食欲不振
- 下痢、腹痛
- 便秘
- 吐き気
「なんとなくお腹の調子が悪い」という症状が長引く場合、その背景には胃腸の冷えが関係している可能性があります。
なぜ夏に胃腸が冷えるのか?その3大原因
1. 冷たい飲食物のとりすぎ
夏は冷たいお茶、ジュース、アイス、そうめん、かき氷など、冷たいものを摂る機会が増えます。胃の中に冷たいものが入ると、胃の血流が低下し、消化酵素の分泌が鈍くなります。
さらに、急激な冷却は自律神経のバランスも崩すため、胃腸の働きが不安定になるのです。
2. 冷房による体の深部冷え
現代の生活では、オフィスや自宅、電車などでエアコンが常に効いている環境が多く、知らないうちに体が冷えてしまいます。特に下半身やお腹周りが冷えることで、内臓温度が下がり、腸の動きが弱くなりがちです。
3. 自律神経の乱れ
胃腸の動きは自律神経にコントロールされています。室内外の温度差が大きい夏は、自律神経の切り替えがうまくいかず、交感神経優位=胃腸の動きが抑制される状態が続いてしまいます。
放っておくとどうなる?慢性化する胃腸トラブル
胃腸の冷えによる不調は、一時的なものであれば自然に改善することもありますが、冷えた生活習慣が続くと慢性化し、以下のような病気につながることもあります。
- 機能性ディスペプシア(原因不明の胃もたれ、吐き気)
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 胃炎、胃潰瘍
- 食欲低下からの栄養失調
「夏は毎年調子が悪い」という方は、症状が出る前の段階で生活を見直すことが重要です。
胃腸の冷えを防ぐための5つの生活習慣
- ① 常温の飲み物を基本にする
つい冷たい飲み物を選びがちですが、なるべく常温〜ぬるめの水やお茶を選ぶのがおすすめです。お腹を温める「白湯」も効果的です。 - ② 食事には温かい汁物をプラス
夏でも1日1回は温かい味噌汁やスープを取り入れましょう。内臓がじんわり温まり、消化が促進されます。 - ③ 冷房を上手に使う
エアコンの温度は26〜28℃を目安に設定し、風が直接当たらないようにしましょう。冷えやすい下半身は、腹巻や薄手のブランケットで守ると◎。 - ④ 湯船にしっかりつかる
夏でもシャワーだけで済ませず、38~40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分つかることで、体の芯から温まり自律神経も整います。 - ⑤ 胃腸にやさしい食材を取り入れる
生姜、ねぎ、にんじん、根菜類、味噌などの体を温める食材を活用しましょう。過剰な冷たい果物や刺激物は控えめに。
胃腸の不調が続くときはご相談ください
「冷えが原因かな?」と思っていても、実は別の病気が隠れていることもあります。
以下のような症状がある方は、一度医師に相談することをおすすめします。
- 胃痛や胸やけが1週間以上続いている
- 食後に強いもたれ感がある
- 急な体重減少
- 血便や黒い便が出る
- 吐き気や食欲不振が慢性的
当院では、症状に合わせて胃カメラ・大腸カメラや腹部エコー・採血など、負担の少ない検査をご提案しています。不安な症状は、我慢せずに早めに受診しましょう。
まとめ
夏の胃腸不調の原因として意外と見落とされがちな「冷え」。
内臓が冷えると、消化吸収や腸の働きが弱まり、全身の体調にも悪影響を与えます。
体の外は暑くても、中は冷えているかもしれません。夏こそ、「冷やしすぎない暮らし」を意識して、胃腸を元気に保ちましょう。
お腹の調子が気になる方、毎年夏に体調を崩してしまう方は、お気軽に当院へご相談ください。
📍 鶴見小野駅前 内科・内視鏡クリニック
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-88-1
JR鶴見線「鶴見小野駅」徒歩1分
📞 045-717-7843