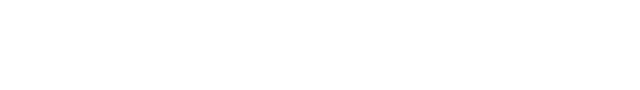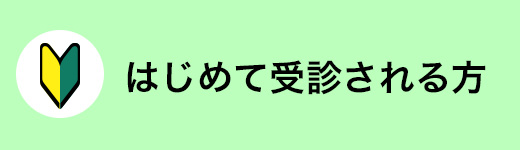食欲の秋に注意!暴飲暴食が招く生活習慣病リスク
「秋は美味しい」「ついつい食べ過ぎてしまう」──そんな声が増える季節です。旬の食材や行楽、食事会が続くと暴飲暴食になりがちですが、これを繰り返すと肥満だけでなく糖尿病、脂質異常症、脂肪肝、高血圧、痛風などの生活習慣病のリスクが高まります。本記事では、なぜ秋に食べ過ぎやすいのか、暴飲暴食が体に及ぼす影響、今日からできる予防法と実践的な食べ方のコツ、受診の目安までを内科の視点でわかりやすく解説します。
目次
- なぜ秋は食欲が増すのか(生理学・環境の要因)
- 暴飲暴食が短期〜長期で招く健康リスク
- 今日からできる具体的な予防法(食事・運動・生活習慣)
- 外食や行事が多いときの賢い対処法
- 受診・検査の目安とクリニックでできること
- まとめ:小さな習慣が大きな差を生む
1. なぜ秋は食べ過ぎやすいのか
秋は「食欲の秋」と呼ばれるように、暑さが和らぎ活動量が増え、農作物や魚介の旬が揃い、レジャーや行楽で外食機会も増える季節です。生理学的には、日照時間の変化や気温低下が食欲を司るホルモン(グレリンやレプチン)に影響することや、夏に消耗した体力の回復としてエネルギー摂取が増える傾向があります。また、季節の行事や飲み会が重なり、短期間で高カロリー食を摂取しやすい環境が整います。
要するに「環境+生理+行動」の三つが揃うため、秋は食べ過ぎリスクが高まります。
2. 暴飲暴食が招く健康リスク(短期〜長期)
短期的な影響
- 消化不良・腹部不快感:食べ過ぎによる胃もたれや胃酸逆流、腹痛。
- 急性の血糖上昇:大量の糖質摂取は一時的に血糖を急上昇させ、倦怠感や眠気を招きます。
- 非特異的な体調不良:頭重感、だるさ、睡眠の質低下。
長期的な影響(生活習慣病リスク)
- 肥満・内臓脂肪の増加:習慣的な過食は体重増加を招き、内臓脂肪がつくとインスリン抵抗性が高まります。
- 2型糖尿病:インスリン抵抗性の進行と膵β細胞の疲弊で血糖コントロール不良に。
- 脂質異常症(高LDL・高トリグリセリド):動脈硬化のリスクが上昇します。
- 非アルコール性脂肪肝(NAFLD):肝臓に中性脂肪が蓄積し、進行するとNASHや肝硬変リスクになります。
- 高血圧:体重増加・塩分過多が血圧を上げます。
- 高尿酸血症・痛風:プリン体やアルコールの過剰摂取で尿酸値が上昇。
- 慢性炎症の増加:肥満に伴う慢性低度炎症はさまざまな疾患のリスク因子です。
こうした変化はゆっくり進行するため、「まだ若いから大丈夫」との油断が命取りになります。早めの対策が重要です。
3. 今日からできる具体的な予防法
暴飲暴食を防ぐには「食べ方」と「生活習慣」の両方を整えることが大切です。以下は実践しやすい方法です。
(A)食べ方の工夫
- 腹八分目を意識する:満腹になるまで食べない。食事中は一度箸を置く習慣を。
- ゆっくり噛む:20〜30回咀嚼を意識すると満腹中枢が刺激されやすい。
- 先に野菜・たんぱく質を食べる:血糖の急上昇を抑え、満足感を得やすい。
- 飲酒時は水をはさむ:アルコールはカロリー源かつ食欲増進因子。水を1杯挟むだけで摂取量が減ります。
- 間食の種類を変える:菓子類をナッツやヨーグルトに替える。甘い飲料は控える。
(B)生活習慣の見直し
- 規則正しい食事時間:食事が不規則だと過食につながりやすい。夜遅い食事は控える。
- 十分な睡眠:睡眠不足は食欲ホルモンを乱し、過食を招く。
- 日常的な運動:速歩30分×週5回を目標に。筋力トレーニングも代謝改善に有効。
- ストレス対策:ストレス食いや過食を防ぐため、趣味・リラックス習慣を持つ。
- 食事日誌をつける:何をどれだけ食べたか記録するだけで摂取が抑えられることが多いです。
(C)栄養の工夫
- 良質なたんぱく質を確保:魚・豆腐・鶏胸肉などで満足感を高める。
- 食物繊維を増やす:全粒穀物、野菜、果物で血糖上昇を緩やかに。
- 適正な脂質を選ぶ:飽和脂肪(脂身・バター)を控え、DHA/EPAやオリーブ油を活用。
- 塩分の節制:加工食品・外食での塩分過多に注意。
4. 外食・行事が多いときの賢い対処法
秋は行楽や会食が増える時期。完全な節制は難しいですが、賢く楽しむコツがあります。
- メニュー選び:揚げ物より焼き物、サラダや蒸し料理を多めに。
- 前菜で野菜を先取り:宴会ではまずサラダやおひたしを食べる。
- 飲酒の量を決めておく:最初に「今日は2杯まで」とルールを作る。
- シェアで満足感アップ:一人で大量に食べるより、みんなで少しずつ味わう方が満足度が高い。
- 移動でカロリー消費:食後に軽い散歩をする習慣をつける。
5. 受診・検査の目安とクリニックでできること
暴飲暴食の影響が心配な場合、または次のような症状があれば医療機関での評価をおすすめします。
- 体重が短期間に増加して止まらない
- 倦怠感や切れ目のない眠気が続く
- 腹部の張り・右上腹部痛(肝臓の負担が疑われる)
- 血糖値や尿検査で異常を指摘された
当院で行える検査例
| 検査 | 目的 |
|---|---|
| 血液検査(血糖・HbA1c・脂質・肝機能) | 糖代謝・脂質異常・肝臓への負担評価 |
| 体組成測定(体脂肪・内臓脂肪の推定) | 肥満のタイプ把握と生活指導 |
| 腹部エコー | 脂肪肝や肝臓病の有無を確認 |
| 尿検査(尿酸) | 痛風リスクの評価 |
検査結果に応じて生活習慣指導、栄養カウンセリング、運動指導、必要時は薬物療法のご提案を行います。
6. 小さな習慣の具体例(1週間チャレンジ)
習慣化しやすい短期プランを紹介します。1週間試してみて、続けられる要素を残しましょう。
- Day1:食事を記録(何をどれだけ食べたか写真でもOK)。
- Day2:野菜を先に1皿食べる。間食をナッツかヨーグルトに変更。
- Day3:夕食のボリュームを7割に。就寝3時間前は食べない。
- Day4:飲酒日を2日に制限。水を1杯挟む。
- Day5:食後に15分の散歩を習慣化。
- Day6:日常動作で階段利用を増やす(目標+1000歩)。
- Day7:体重・腹囲を計測し、1週間の変化を確認。
1週間で大きな変化は難しくても、自覚が高まり次の行動につながります。
まとめ
- 秋は食欲や行事が増え、暴飲暴食に陥りやすい季節です。
- 短期的な不快感だけでなく、習慣的な過食は糖尿病・脂質異常・脂肪肝・高血圧などの生活習慣病を招きます。
- 腹八分目、先に野菜・たんぱく質、睡眠・運動・水分管理などの基本を守ることが予防の要です。
- 外食や行事は工夫して楽しみつつ、検査が必要なら早めに医療機関へ。
食べることを楽しむのは人生の喜びの一つ。しかし「習慣」にしてしまわないためのセルフコントロールが健康を守ります。まずは今日の1食を少しだけ見直してみましょう。
横浜市鶴見区で生活習慣が気になる方へ
鶴見小野駅前内科・内視鏡クリニックでは、血液検査・腹部エコー・生活習慣改善の個別指導を行っています。食欲の秋を健康的に楽しむための相談もお気軽にどうぞ。
📍 鶴見小野駅前 内科・内視鏡クリニック
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-88-1
JR鶴見線「鶴見小野駅」徒歩1分
TEL:045-717-7843
Web予約・アクセス ▶ https://tsurumi-ono.clinic