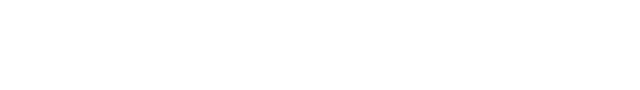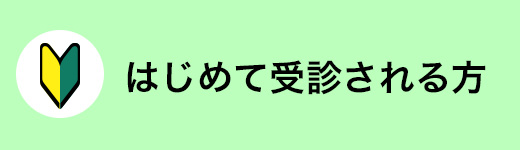肝臓内科
肝臓内科とは?─肝臓の病気を早期発見・適切に治療するために
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、自覚症状が出にくいため病気の発見が遅れやすい臓器です。しかし、肝疾患は進行すると肝硬変や肝がんに至ることがあり、早期発見・治療が重要です。
当院「鶴見小野駅前内科・内視鏡クリニック」では、肝機能異常の評価から、脂肪肝、ウイルス性肝炎、肝硬変、肝がんに至るまで、肝臓内科領域の幅広い診療を行っております。
肝臓の主な働き
- 代謝機能(糖質・脂質・タンパク質)
- 解毒作用(薬剤・アルコールの分解)
- 胆汁の生成・分泌
- ビタミンや糖の貯蔵
肝臓はこれらの働きを通じて、私たちの体を支える重要な臓器です。
肝臓内科で扱う主な疾患
脂肪肝・代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)
脂肪肝は現代人に増えている病気で、肥満や糖尿病、高脂血症などが原因です。進行すると代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)となり、肝硬変や肝がんのリスクもあります。
主な治療: 食事・運動療法、生活習慣病の管理、定期的な血液検査と超音波検査
ウイルス性肝炎(B型・C型)
B型・C型肝炎はウイルスによって肝臓が炎症を起こす疾患です。C型肝炎は現在、経口薬で完治可能な時代となりました。
主な検査・治療: ウイルスマーカー検査、抗ウイルス薬、ワクチン(B型)
肝硬変
慢性肝障害が続くことで肝臓が線維化し硬くなる状態です。黄疸や腹水、意識障害などがみられることがあります。
治療: 原因疾患の治療、栄養療法、薬物療法、定期的な肝がん検診
肝がん
肝炎や肝硬変を背景に発症することが多く、定期的な画像検査での早期発見が鍵となります。
検査・治療: 腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-II)、超音波・CT・MRI、外科的切除やラジオ波治療など
薬剤性肝障害
薬やサプリメント、漢方薬などが原因で肝障害を引き起こすことがあります。原因薬剤の中止により回復する場合が多いです。
自己免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎(PBC)など
体の免疫が自身の肝臓を攻撃してしまう特殊なタイプの肝炎です。
当院で行っている検査・診療
- 血液検査(AST, ALT, γ-GTPなど)
- ウイルスマーカー(HBs抗原、HCV抗体)
- 腹部エコー
- 栄養・生活習慣指導
- 必要に応じて専門機関との連携
このような症状・お悩みはありませんか?
- 健診で肝機能異常を指摘された
- 倦怠感や食欲不振が続いている
- 黄疸やむくみが気になる
- 肝炎の家族歴がある
- 以前に脂肪肝と言われたことがある
このような場合は、ぜひ一度当院の肝臓内科を受診ください。
まとめ
肝臓は症状が現れにくい臓器のため、定期的な検査や早期の専門受診が大切です。肝臓内科では、脂肪肝・ウイルス性肝炎・肝硬変・肝がんなどの診断と治療を行い、患者様の健康維持をサポートいたします。
当院では、地域の皆さまの肝臓の健康を守るべく、丁寧でわかりやすい診療を心がけております。些細なことでもお気軽にご相談ください。