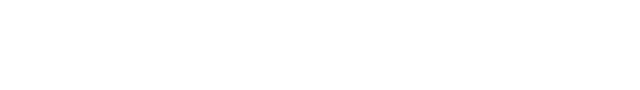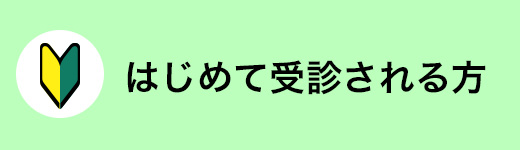肝機能障害とは?
肝機能障害とは、肝臓の働きが低下した状態を指します。肝臓は、代謝・解毒・胆汁の生成・エネルギー貯蔵など、人間の生命活動に欠かせない重要な臓器です。日常の血液検査で「肝機能異常」と指摘されることは珍しくなく、多くは自覚症状が乏しいため、健康診断で初めて異常を知る方も多いです。
肝機能障害の背景には、アルコール、脂肪肝、ウイルス性肝炎、薬剤性障害などさまざまな原因があります。放置すると肝硬変や肝がんに進行する可能性もあるため、早期の診断・治療が重要です。
肝臓の主な働き
- 栄養素の代謝(糖、脂質、タンパク質)
- アンモニアなど有害物質の解毒
- 胆汁の生成・分泌(脂肪の消化を助ける)
- 薬剤やアルコールの分解
- 血液の貯蔵や止血因子の合成
肝機能障害の主な原因
■ 脂肪肝・代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)
肥満・糖尿病・高脂血症などが背景にあり、生活習慣に起因。特に進行型の代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)は、将来的に肝硬変や肝がんのリスクがあります。
■ アルコール性肝障害
長期間にわたる過剰飲酒が原因。アルコール性脂肪肝 → 肝炎 → 肝硬変と進行することもあります。
■ ウイルス性肝炎(B型・C型など)
感染により肝細胞が障害され、慢性化することで肝硬変や肝がんのリスクにつながります。
■ 薬剤性肝障害
一部の薬剤(解熱鎮痛薬、抗生物質、漢方など)や健康食品によって肝障害を起こすこともあります。
■ 自己免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎(PBC)など
体の免疫が自身の肝臓を攻撃してしまう特殊なタイプの肝炎です。
肝機能障害の症状
多くの場合、初期は無症状ですが、進行すると以下のような症状が出現することがあります。
- 倦怠感、疲れやすさ
- 食欲不振、体重減少
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
- かゆみ
- 腹部膨満感(腹水)
- 手掌紅斑、クモ状血管腫(肝硬変の兆候)
血液検査でわかる肝機能障害のサイン
健診などで以下の項目に異常があると、肝機能障害が疑われます。
- AST(GOT)、ALT(GPT):肝細胞の障害を反映
- γ-GTP:アルコールや脂肪肝、胆道系の異常
- ALP、ビリルビン:胆汁の流れの障害
- Alb(アルブミン)、PT(プロトロンビン時間):肝臓の合成能力を評価
診断と追加検査
血液検査に加えて、以下のような検査を必要に応じて行います。
- 腹部エコー(超音波検査):脂肪肝、肝腫瘤、胆道の異常の確認
- 腹部CT・MRI:より精密な画像診断
- ウイルスマーカー検査:B型・C型肝炎の有無
- Fib-4 index、M2BPGiなどの線維化マーカー
- 肝生検:必要に応じて肝臓の組織診断
治療と対応
治療は原因に応じて異なります。
- 脂肪肝・生活習慣病が原因:食事・運動・減量・糖尿病や脂質異常の管理
- アルコール性肝障害:禁酒が最も重要
- ウイルス性肝炎:抗ウイルス薬やインターフェロン療法
- 薬剤性肝障害:原因薬剤の中止
- 自己免疫性肝炎:ステロイドなど免疫抑制治療
また、定期的な血液検査や画像検査による経過観察が不可欠です。
当院での対応について
当院では、肝機能異常を指摘された患者様に対して、原因の特定と生活指導、必要に応じた検査・治療を行っております。脂肪肝やウイルス性肝炎、薬剤性肝障害など幅広く対応可能です。
健診で「肝機能の異常」を指摘された方、倦怠感や食欲不振が続く方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
肝機能障害は、症状が現れにくく気づかれにくい病気ですが、放置すると重篤な病気につながることもあります。定期的な検診と適切な生活習慣、早期の医療介入で肝臓の健康を守りましょう。