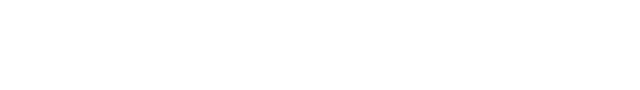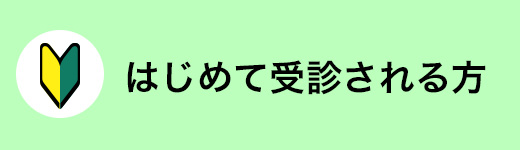感染性胃腸炎とは?
感染性胃腸炎とは、ウイルスや細菌などの病原体が胃や腸に感染して、嘔吐・下痢・腹痛・発熱などの症状を引き起こす病気です。特に冬季に流行しやすいウイルス性胃腸炎(いわゆる「おなかの風邪」)は、子どもから高齢者まで幅広く感染します。細菌性のものは、夏場の食中毒が代表的で、原因となる食品の摂取によって起こります。
主な原因と種類
感染性胃腸炎は、原因となる病原体によって以下のように分類されます。
1. ウイルス性胃腸炎
ノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスなどが原因です。
- ノロウイルス:冬季に流行し、少量のウイルスでも感染力が強い
- ロタウイルス:乳幼児に多く、嘔吐・激しい下痢が特徴
- アデノウイルス:年中みられますが特に夏場に多い
2. 細菌性胃腸炎
カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌(O157など)が代表的です。
- 食べ物や水を通じて感染
- 高熱・血便を伴うことがあり、ウイルス性より重症化しやすい傾向があります
3. 寄生虫による胃腸炎
日本ではまれですが、アメーバ赤痢やジアルジア症などが海外渡航歴のある方に見られることがあります。
主な症状
- 吐き気・嘔吐
- 下痢(水様便や粘液便、時に血便)
- 腹痛・腹部膨満感
- 発熱(特に細菌性)
- 全身倦怠感や食欲不振
症状は数日〜1週間ほどで自然に回復することが多いですが、高齢者では脱水や重症化に注意が必要です。
感染経路と予防策
■ 感染経路
- 飛沫感染(嘔吐物や下痢便の飛散)
- 接触感染(ウイルスがついた手で口に触れるなど)
- 経口感染(汚染された食品・水の摂取)
■ 予防策
- 手洗いの徹底(石けんと流水で30秒以上)
- 調理器具や食品の衛生管理(加熱・消毒)
- 嘔吐物・便の適切な処理と消毒
- 感染者との接触を避ける
ノロウイルスにはアルコール消毒が効きにくく、次亜塩素酸ナトリウムの使用が有効です。
診断と治療
■ 診断と検査
- 便培養検査(細菌性を疑う場合)
- 血液検査
便培養検査では細菌性胃腸炎を疑う場合に行います。また脱水などが疑われ症状が強い場合は血液検査も行います。
■ 治療
多くの場合、対症療法(症状を和らげる治療)が中心となります。
- 絶食などによる腸管の安静
- 脱水予防のための水分補給(経口補水液など)
- 自己判断での下痢止めは避ける(悪化のリスク)
- 必要に応じて整腸剤や吐き気止めを処方
- 細菌性で重症の場合は抗生物質を使用することも
胃腸炎の一番の治療は腸管の安静と脱水予防の水分摂取が重要です。下痢が続くため下痢止めを内服する方がいますが感染性胃腸炎の場合下痢を止めてしまうと悪化してしまうため下痢止めは避けてください。
受診の目安
- 高熱や血便がある
- 嘔吐・下痢が続き水分が取れない
- 強い腹痛がある
- 高齢者・基礎疾患がある方で症状が強い
- 集団生活中で感染拡大が懸念される場合
感染拡大を防ぐために
感染性胃腸炎は、ご本人だけでなくご家族や職場・学校に広がる可能性があります。
- 発症後は外出を控える
- 手洗いを徹底する
- 症状が治まってからもウイルスはしばらく排出されるため注意が必要
当院での対応について
当院では、感染性胃腸炎が疑われる患者様に対し、迅速な診察・脱水予防・必要な検査を行っております。また胃腸炎と思っていたら別の疾患が隠れていることもあります。気になる症状があれば専門医への相談が望ましいため気軽にご相談ください。
まとめ
感染性胃腸炎は非常に身近な病気ですが、早めの対応と予防意識がとても大切です。手洗いなどの日常的な衛生管理を徹底し、症状が現れた際には自己判断せず当院へご相談ください。